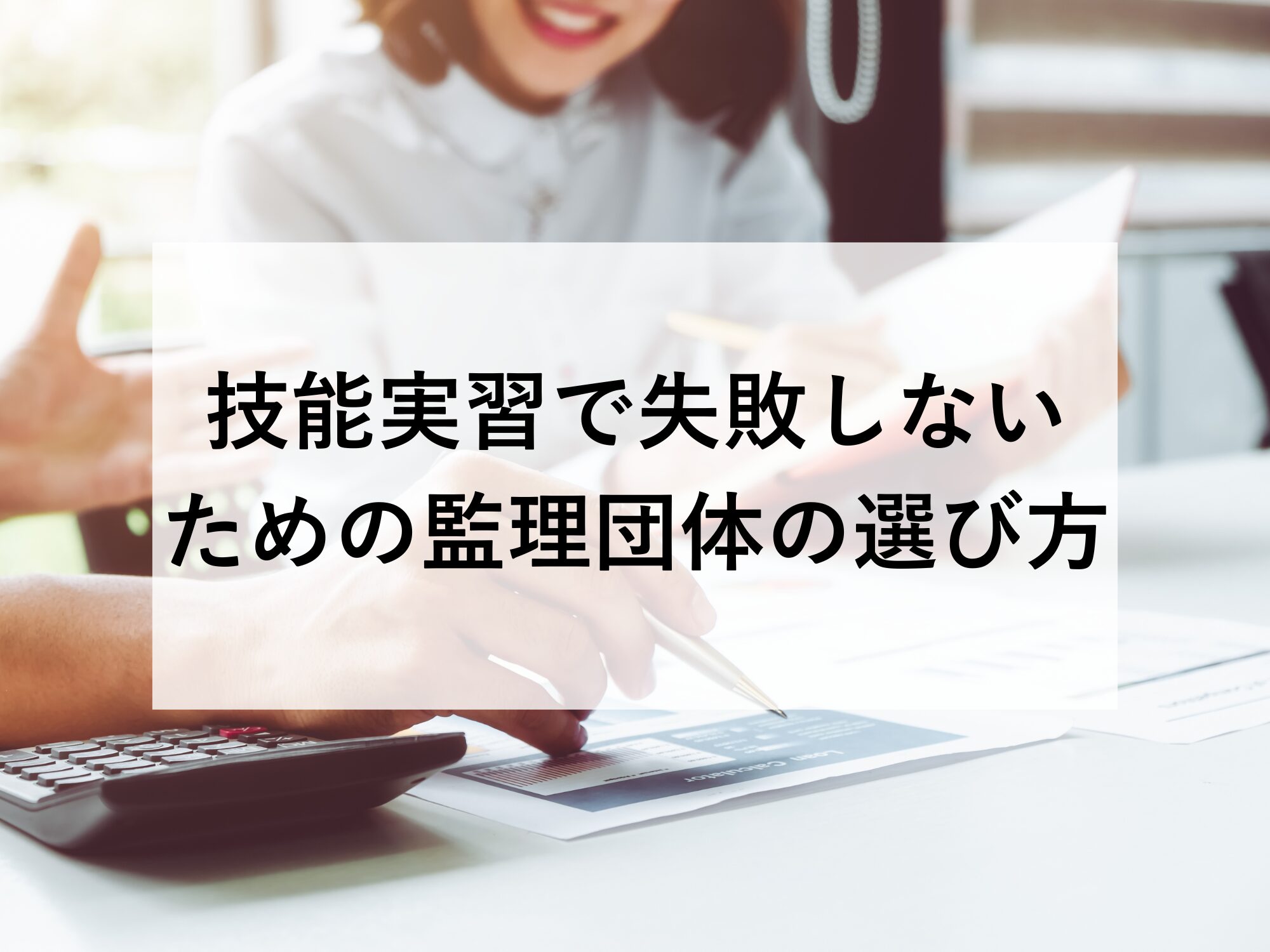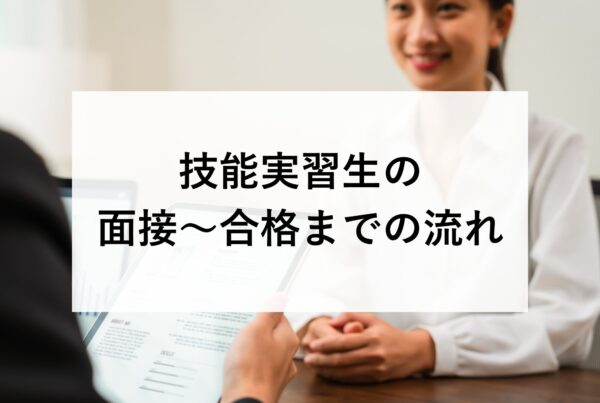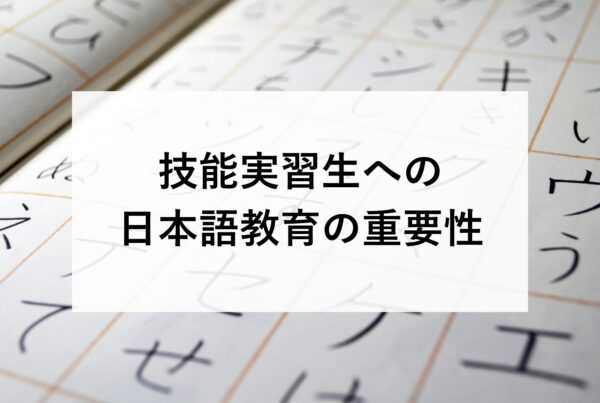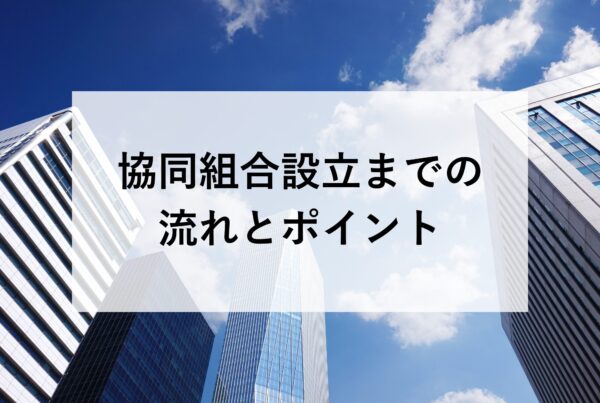はじめに
技能実習制度を活用して外国人材を受け入れる企業が増える中で、「思った人材と違った」「すぐ辞めてしまった」「サポートがまったく届かない」といった声を耳にすることも少なくありません。これらのトラブルの理由の1つに、協同組合(監理団体)の選定ミスに起因しています。本記事では、制度の仕組みや現場での実態をもとに、失敗しない協同組合の選び方を解説します。
協同組合とは?その役割
協同組合とは、複数の企業が共同で設立する非営利法人で、技能実習制度では「監理団体」としての役割を担います。技能実習事業における主な役割は以下の通りです。
- 実習計画の作成・申請支援
- 受入企業と実習生のマッチング
- 定期的な実地訪問と監査
- 実習生の生活支援・相談対応
つまり、監理団体は実習生と受入企業の間に入り、制度を適正に機能させる責任を持っています。
技能実習で起こる典型的な失敗事例
以下のような問題が、技能実習生を受入した企業で実際に起きています。
- 実習生の失踪
- 実務内容と適性のミスマッチ
- 企業や実習生への説明不足・誤解
- トラブル発生時の連絡が取れない
特に失踪については、大きな問題として取り上げられております。
失踪が起きる本当の背景
① 海外でクオリティの高い人材が集まりにくくなっている
かつて日本は「人気の海外就労先」でしたが、近年は円安の影響で状況が変わっています。同じ期間働くのであれば、中東や英語圏のほうが収入が高く、優秀な人材がそちらに流れる傾向が強まっています。特にフィリピンのように英語を第二言語として話す国では、その傾向が顕著です。
② 技能実習生が借金を抱えた状態での入国 実習生が失踪する背景には、現地・日本双方に問題があります。
◾️現地の問題
不当なブローカーが介入し、必要以上に技能実習生に費用を請求している
◾️日本側の問題
監理団体が現地の送出し機関にキックバックを要求。これにより、送出し機関は費用回収のために実習生から過剰徴収を行うという構図が生まれます。このように、本来守られるべき実習生が最も搾取される仕組みになってしまっていることが、失踪やトラブルの温床になっています。また、監理団体が現地の送出し機関にキックバックを要求する背景は、資金が不足していることが殆どです。資金が不足している理由の主は、技能実習生の受入人数が足りていないからです。
良い監理団体の4つの特徴
では、受入企業はどのような監理団体を選ぶべきなのでしょうか?
私たちの経験を通じて、「良い監理団体」には以下の4つの特徴があると考えています。
- クオリティの高い人材を安定して紹介できる
ここでの「クオリティの高さ」とは、「日本語能力がある」「失踪しない人材」であることです。 - 外国人材の雇用やマネジメント経験がある
単なる監理団体としての事務的な業務にとどまらず、自ら外国人材を雇用・マネジメントした実績がある監理団体は、定着支援においても実践的なノウハウを持ち合わせています。そのため、現場目線に立ったアドバイスや対応が可能となり、企業にとってより安心できるパートナーとなります。 - レスポンスが早い
トラブル時の初動が遅ければ、信頼関係も崩れてしまいます。 - 外国人材への想いや情熱がある
実習生の成長に本気で向き合い、受入企業への貢献を考えられるパートナーであるかが重要です。
当記事をお読みの方にとっては、当たり前と思う内容かもうしれませんが、この当たり前のことをできていない監理団体が多く実在するのも事実です。
アイボウ協同組合の強みと全体最適の仕組み
私たちAIBOUグループは、技能実習制度の本来の趣旨に則り、実習生の成長を通じて受入企業の発展に貢献することをモットーとしています。技能実習期間中に、実習生が受入企業としっかりマッチし、現場で技術を磨くことで、特定技能への在留資格変更後も継続的にその企業で働き続けられる環境を目指しています。これにより、実習生はさらなるスキルアップが可能となり、受入企業にとっては中長期的な人材確保という大きなメリットを生み出すことができます。
◾️インドネシアに自社の送出し機関(AIBOUインドネシア)を経営
候補者の選定・教育・ビザ管理の一貫対応
◾️アイボウ協同組合が監理を担当
来日後も現地との連携を密に取り、生活・定着までフォロー
まとめ
技能実習制度を成功させるカギは、「どの監理団体に依頼をするか」にあります。人材の質、対応力、想い -これらすべてが企業の現場に影響を及ぼします。
アイボウ協同組合では、実習生・企業・制度の三方にとって最適な形を提供できるよう、日々改善と対話を重ねています。これから技能実習制度を検討される企業様は、「パートナー(監理団体)選び」にもぜひ目を向けてみてください。