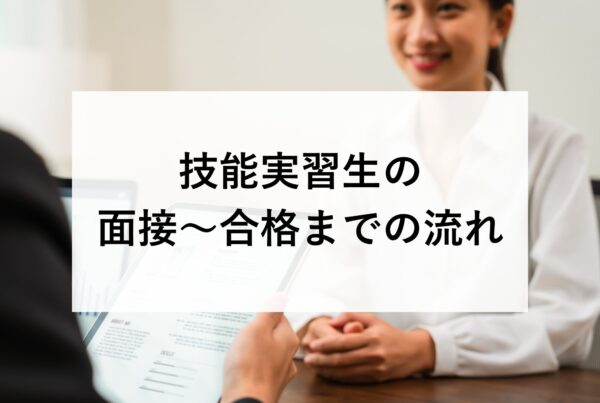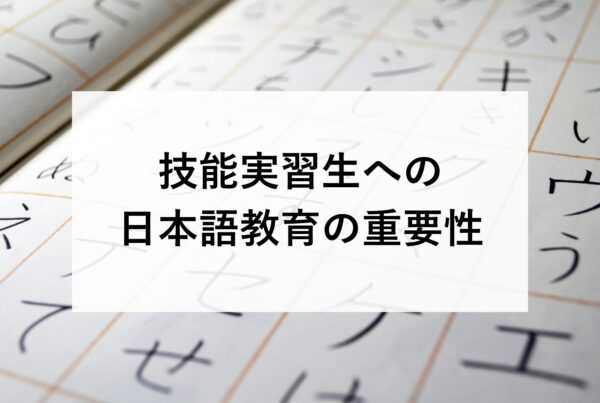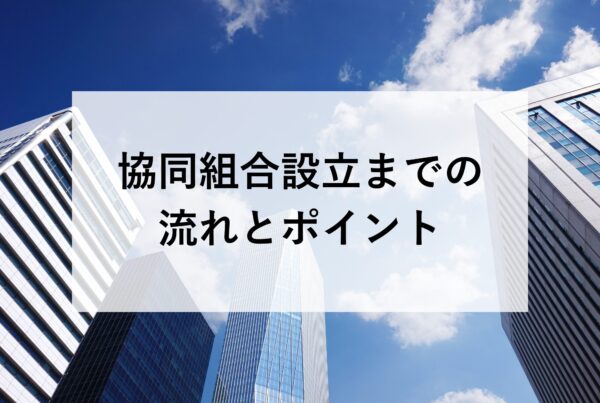はじめに
技能実習制度を活用する企業が増加するなか、「実習生の日本語力不足によるトラブル」も少なくありません。作業指示が伝わらない、職場での孤立、事故リスクの増加——これらはすべて「日本語力」が深く関係しています。本記事では、技能実習生に対する日本語教育の現状とその重要性、そして私たちAIBOUグループが行う独自の教育体制について解説します。
技能実習生は入国前にどんな日本語学習をしているのか?
一般的に、技能実習生は内定後から約6ヶ月間、現地の送出し機関にて日本語教育を受けます。この期間で目指すのは、日本語能力試験(JLPT)のN5レベル。N5は、簡単なあいさつ・数字・自己紹介レベルの会話が可能になる基礎的な水準です。
ただし、教育の開始時期や学習時間は国・機関によって大きく異なり、教育体制が整っていない送出し機関では、面接通過後に形式的な講義だけ行い、十分な日本語力を身につけさせないまま出国させることもあります。
入国時の日本語力はどれくらい?
現実には、入国時点の技能実習生の日本語力には大きなバラつきがあります。JLPTやJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)などのスコアがN5相当であっても、「実際に話せるか」という点ではまた別問題です。
【実際の例】
- N5取得済だが、ひらがなすら読めない
- 「はい」と答えるが内容を理解していない
- 「休む」「遅れる」「危ない」など、重要語彙を知らない
このような状態で現場に配属されると、指示が通らず、事故やトラブルの原因になることがあります。
国籍別の日本語力比較(参考)
| 国籍 | 日本語力の平均的傾向 | コメント |
| インドネシア | ◎ | 母国語の発音や語順が日本語に似ていて習得しやすい日本語学習者が多い |
| ミャンマー | ◎ | 母国語の文法構造が日本語に近い日本語学習者が多い |
| ベトナム | ◯ | 日本語の発音に難しさを感じるが、母国語の影響で文法的は学習しやすい |
| フィリピン | △ | 英語習得が簡単な彼らにとって英語から1番言語が離れている日本語は難しい。 |
このように母国語に影響を受けて日本語の習得スピードに差が生じます。実際に日本人が英語習得に苦戦するのと同じように、日本語から言語距離が離れている言語を第一言語とする人には日本語習得が非常に難しいです。
なぜ日本語力が低い実習生が存在するのか?
実習生の日本語力が不十分な背景には、主に以下のような理由があります。
- 基準が低い
→ 日本の受入企業がどれくらいの日本語力を求めているか理解をしていない - 送出し機関がキックバック重視
→ 現地での学習体制に重きを置いていない - 内定後にしか教育を始めない
→ 待機人材を持たないため、短期間で教育せざるを得ない - 実習生本人のモチベーション不足
→ フィリピンのような国では真面目でモチベーションの高い優秀人材は日本以外の国を目指す傾向も
このように、構造的な問題が日本語力の低下を招いているのが実情です。
日本語力が低いと起きる現場の問題
日本語力が十分でない場合、企業や現場では以下のような問題が発生します。
- 安全指示が理解できず、ケガや事故のリスクが増す
- 報連相ができず、トラブルが拡大する
- 職場内で孤立しやすく、精神的に不安定になる
- 周囲のスタッフの負担が増える(通訳・確認など)
- 定着率が大きく下がる(不安→退職・失踪)
つまり、日本語力は「安全・定着・成果」すべてに直結する土台なのです。ここで、筆者の実体験を一つ紹介します。

先日、ある大手飲食チェーン店でランチを取った際のことです。店内は、日本人スタッフ2名と、特定技能で就労しているベトナム人スタッフ1名という体制で営業していました。ところがこのベトナム人スタッフは日本語力が非常に乏しく、業務中に何度も日本人スタッフから注意を受けていました。しかも、その注意(というよりは説教に近いものでした)は、スタッフ本人が十分に理解できておらず、結果的に同じ内容が繰り返されていました。さらに問題だったのは、それがお客様の目の前で行われていたことです。飲食中の身として、とても残念な気持ちになったのを覚えています。もちろん、これは本人の責任だけではありません。本質的な問題は、彼が就労に至るまでの「面接」や「内定後の日本語教育体制」、さらには、その日本語力のまま人材を紹介した現地送り出し機関、そしてそれを見抜けなかった採用企業側の選考プロセスにもあると感じました。
AIBOUグループの取組
AIBOUグループでは、「日本語教育は人材のクオリティを左右する」という考えのもと、以下のような取り組みを行っています。
- 内定前から教育開始できる日本語学校機能付きの送出し機関を設立(AIBOUインドネシア)
- 入国までの学習期間は平均1年間(通常の2〜3倍)
- 候補者とは日本語で面接実施
- 実用日本語に特化したカリキュラムで会話力を重視
実際、AIBOUインドネシアの技能実習生は入国前にN4会話が可能であり、受け入れ企業から「教育レベルが他と全く違う」という評価を多数いただいています。

まとめ
技能実習生の日本語力は、「制度を活用できるかどうか」の鍵を握る重要要素です。
教えれば伸びる——ではなく、受け入れ前の段階でどこまで仕上がっているかが成功の分かれ目になります。企業側も、「送り出し機関任せ」ではなく、どの機関と組むか、日本語教育がどう行われているかまでチェックする必要があります。AIBOUグループでは、教育の質にこだわり、企業と実習生双方の「最初の一歩」を支援します。「日本語力でトラブルを避けたい」「レベルの高い実習生を受け入れたい」という企業様は、ぜひ一度ご相談ください。